
奈良県で眼瞼下垂治療が
選ばれる5つの理由
皮膚科・形成外科専門医による
質の高い診断と治療
当院は、長年の経験を持つ形成外科専門医が、患者様のまぶたの状態を詳細に診察します。眼瞼下垂の原因は多岐にわたるため、正確な診断が治療成功の第一歩です。当院の専門医は、それぞれの患者様に最適な治療法を見極め、確かな技術で質の高い治療を提供します。
患者様一人ひとりの症状や
ライフスタイルに合わせた治療
眼瞼下垂の症状は患者様によって様々です。当院では、画一的な治療ではなく、患者様のご希望や生活習慣、お仕事などを考慮し、最適な治療計画を一緒に考えます。手術方法だけでなく、術後の生活指導まで、患者様に寄り添ったプランを提案することで、より満足度の高い結果を目指します。
最新の医療設備と
技術を導入し、より安全で
効果的な手術を提供
安全で精度の高い手術は、患者様の不安を軽減し、より良い結果をもたらします。飯岡形成外科ひふ科では、眼瞼下垂治療のために、高周波メスや炭酸ガスレーザーなどの最新の医療設備を導入し、熟練した技術を持つ医師が手術を行います。これにより、手術の安全性と効果を最大限に高め、患者様が安心して治療を受けられる環境を整えています。
術後の経過観察を徹底!
安心のアフターフォロー
眼瞼下垂の治療は、手術が終わればそれで終わりではありません。術後の適切なケアが、回復を早め、より自然な仕上がりへと導きます。当院では、手術後の経過観察を丁寧に行い、腫れや内出血への対処法、日常生活での注意点などを細かく指導します。何か不安な点があれば、いつでも相談できる体制を整え、患者様の回復をきめ細やかにサポートします。
地域に根差したクリニック
として、温かく丁寧な対応
奈良県桜井市の地域医療の一員として、当院は患者様とのコミュニケーションを大切にしています。診察から治療、アフターケアまで、患者様が安心して何でも相談できるような温かい雰囲気作りを心がけています。スタッフ一同、患者様お一人おひとりに寄り添い、丁寧な対応で皆さまの健康をサポートいたします。
眼瞼下垂に対する院長の想い
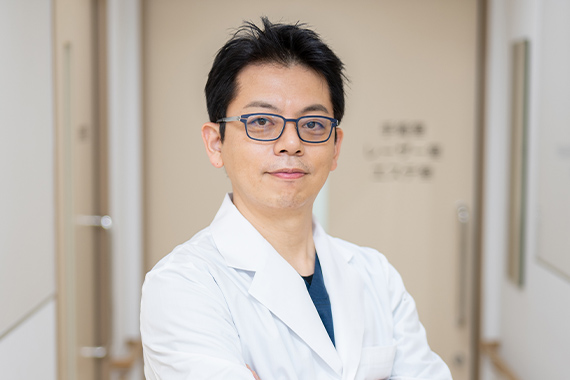
当院は地域に根ざした皮膚科・形成外科として、皆さまの美と健康をサポートできるよう日々努めております。特に眼瞼下垂は、見た目の問題だけでなく、日常生活にも大きな影響を及ぼす疾患です。
まぶたが下がることで視野が狭まったり、額にシワが増えたり、頭痛や肩こりを引き起こすこともあります。当院では、患者様一人ひとりの症状や悩みに真摯に向き合い、最適な治療法をご提案いたします。
患者様が自信を持って笑顔で過ごせるよう、丁寧なカウンセリングと確かな技術でサポートすることをお約束いたします。
こんなお悩みありませんか
- 朝、目が開きにくいと感じることがある
- 眉毛を上げて物を見る癖がある
- 視界が狭く感じ、見えにくい
- 肩こりや頭痛が慢性的に続いている
- 額のシワが深くなった気がする
- 目が疲れやすい、目がしょぼしょぼする
眼瞼下垂とは

眼瞼下垂とは、まぶたが正常な位置よりも下がり、瞳孔の一部または全部を覆ってしまう状態を指します。
まぶたを持ち上げる筋肉の力が弱くなったり、まぶたの皮膚がたるんだりすることで起こります。
見た目の問題だけでなく、視野の障害から視機能にも影響を与えます。当院は奈良県桜井市の皮膚科・形成外科として、この眼瞼下垂の治療に力を入れています。
眼瞼下垂は、年齢を重ねるにつれて発症する方が多いですが、若い方にも見られることがあります。
眼瞼下垂になる理由・原因
①腱膜性眼瞼下垂:加齢・コンタクトレンズの長期使用・白内障などの手術後などに起こります。まぶたを持ち上げる挙筋腱膜が、加齢や物理的な力により伸びたり、付着部(瞼板)から外れてゆるんだりすることで起こります。最も一般的な原因です。
②まぶたの皮膚のたるみ:加齢によりまぶたの皮膚がたるみ、視界を遮ることがあります。これは皮膚弛緩症とも呼ばれ、腱膜性眼瞼下垂と併発することもあります。
③その他 先天性のもの:生まれつきまぶたを持ち上げる筋肉の発達が不十分な場合に起こります。神経の異常によるもの:まぶたを動かす神経に異常がある場合に起こります。
眼瞼下垂を受ける前に
知っておいてほしいこと
眼瞼下垂手術は、まぶたの機能を回復させ、視野を改善しその結果若々しい印象を与える効果が期待できますが、手術である以上、いくつかの注意点があります。まず、術後には腫れや内出血が生じることがあり、個人差はあるものの、通常1〜2週間程度で落ち着きます。
ただし、完全に腫れが引くには数ヶ月かかる場合もあります。また、人の顔はもともと左右対称ではないため、手術後も完全な対称にはならず、自然な仕上がりを目指して行います。
切開を伴う手術の場合は傷跡が残りますが、できるだけ目立たないよう配慮しています。時間の経過とともに目立ちにくくなることがほとんどです。
さらに、ごくまれに感染や出血、目が閉じにくくなるといった合併症が起こる可能性もあります。眼瞼下垂は加齢によって再発することもあるため、長期的な視点も必要です。奈良県桜井市の飯岡形成外科ひふ科では、形成外科の専門医が、これらのリスクを丁寧にご説明し、患者様が安心して治療を選択できるようサポートしております。ご不明な点があれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。
眼瞼下垂の治療方法
保険診療による治療
機能的な問題(視野の狭さ、頭痛、肩こりなど)がある場合、保険診療が適用されることがあります。
挙筋前転法:まぶたを持ち上げる筋肉(眼瞼挙筋)の力を強める手術です。ゆるんだ挙筋腱膜を短縮したり、瞼板に縫い付けたりすることで、まぶたの開きを改善します。
余剰皮膚切除術:まぶたの皮膚がたるんでいる場合に、余分な皮膚を切除することで視界を広げます。眼瞼下垂と併発している場合に行われることがあります。
眼瞼下垂を受ける前に
知っておいてほしいこと
美容的な改善を主目的とする場合や、保険診療の対象とならない場合は、自費診療となります。
二重形成術を併用した眼瞼下垂手術:より自然で美しい二重ラインを形成しながら、眼瞼下垂を改善します。
眉下切開:眉毛の下のラインに沿って皮膚を切除し、まぶたのたるみを引き上げます。比較的ダウンタイムが短いという特徴があります。
眼瞼下垂の治療の流れ
01診察・カウンセリング
まずは患者様のまぶたの状態を詳しく診察し、お悩みやご希望を丁寧に伺います。眼瞼下垂の程度、原因、既往歴などを確認します。
02検査
まぶたの開き具合を測定する検査を行います。これらの検査は、手術の適応や術式の選択に重要な情報となります。
03手術計画のご提案
診察と検査の結果に基づき、患者様一人ひとりに最適な治療法と手術計画を詳しくご説明します。保険適用となる場合と自費診療となる場合の費用の説明も行います。
04手術
手術は局所麻酔で行います。当院は日帰り手術が可能です。患者様が安心して手術を受けられるよう、痛みを最小限に抑え、丁寧な処置を心がけます。
05術後検診・アフターケア
手術後は、定期的に検診を行い、回復状況を確認します。経過観察はもちろん、ご自宅でのケア方法や注意点についても詳しくご説明します。何かご不明な点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。
眼瞼下垂のよくある質問
眼瞼下垂の手術は痛いですか?
手術は局所麻酔を使用するため、手術中の痛みはほとんど感じません。麻酔を打つ際にチクっとした痛みを感じることはありますが、すぐに麻酔が効いてきます。手術後は麻酔が切れると多少の痛みを感じることがありますが、痛み止めを処方しますのでご安心ください。奈良県桜井市の飯岡形成外科ひふ科では、患者様の痛みを最小限に抑えるよう配慮し、皮膚科・形成外科の専門医が丁寧な手術を行います。
手術後、どれくらいで日常生活に戻れますか?
1週間程度は大きな腫れが続きますが、手術翌日から通常の生活は可能です。しかし、激しい運動や飲酒、長時間の入浴などは数日間控えていただく必要があります。また、腫れや内出血が引くまでの間は、目元をあまり刺激しないようにしてください。
手術後の腫れはどのくらい続きますか?
手術後の腫れは、個人差や手術方法によって異なりますが、一般的には術後2~3日がピークで、その後徐々に引いていきます。大きな腫れは1~2週間程度で落ち着き、内出血も同程度の期間で薄くなります。
保険は適用されますか?
眼瞼下垂の治療は、機能的な問題(視野の狭さ、頭痛、肩こりなど)があり、日常生活に支障をきたしていると判断された場合に、保険診療の適用となることがあります。美容目的の場合は、自費診療となります。
手術を受けられないケースはありますか?
特定の持病をお持ちの方や、服用している薬によっては手術を受けられない場合があります。例えば、血液をサラサラにする薬を服用している場合は、一時的に中止していただく必要があります。また、極度の高血圧や糖尿病、心臓病などの持病がある場合は、主治医と相談の上、慎重に検討する必要があります。妊娠中の方も、原則として手術は行いません。
まずは一度、奈良県桜井市の飯岡形成外科ひふ科にご相談いただき、皮膚科・形成外科の専門医が患者様の状態を詳しく確認させていただきます。
著者情報
飯岡 弘至Hiroshi Iioka
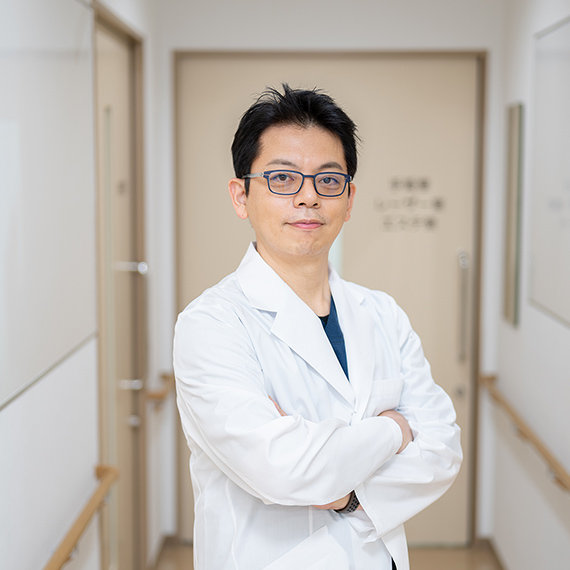
院長・医師
略歴
-
- 平成12年
- 近畿大学医学部 卒業
-
- 平成12年
- 奈良県立医科大学皮膚科、形成外科に入局
-
- 平成17年
- 奈良県立医科大学 助教
-
- 平成28年
- 奈良県立医科大学 退職
-
- 平成29年1月
- 飯岡形成外科ひふ科 開院
資格・所属学会
- 日本専門医機構認定 形成外科領域専門医
- 日本形成外科学会認定 皮膚腫瘍外科分野指導医
- 日本皮膚科学会認定 皮膚科専門医
